
エレキベースって、メーカーいろいろありますよね。

そうですね。
メーカーによって特徴も違いますね。
知っておくと楽器を選ぶ時に役立ちますよ。

それぞれのメーカーの特徴を
教えてください。

了解です。
僕が知っている限りのことを教えますね。

よろしくです。
こちらの記事では有名なベーシストが愛用する楽器や機材を紹介しています。こちらも合わせてご覧ください。
- エレキベースのメーカー その1 Fender
- エレキベースのメーカー その2 Fodera
- エレキベースのメーカー その3 Squier (by Fender)
- エレキベースのメーカー その4 ATELIER Z
- エレキベースのメーカー その5 Bacchus
- エレキベースのメーカー その6 DINGWALL
- エレキベースのメーカー その7 FUJIGEN
- エレキベースのメーカー その8 Gibson
- エレキベースのメーカー その9 Hofner
- エレキベースのメーカー その10 Ibanez
- エレキベースのメーカー その11 Xotic
- エレキベースのメーカー その12 LAKLAND
- エレキベースのメーカー その13 MUSICMAN
- エレキベースのメーカー その14 momose
- エレキベースのメーカー その15 Moon
- エレキベースのメーカー その16 Rickenbacker
- エレキベースのメーカー その17 Sadowsky Guitars
- エレキベースのメーカー その18 STEINBERGER
- エレキベースのメーカー その20 Warwick
- エレキベースのメーカー その21 YAMAHA
- エレキベースのメーカー その22 Aria ProII
- エレキベースのメーカー その23 MAYONES
- エレキベースのメーカー その24 SPECTOR
- エレキベースのメーカー その25 G&L
- エレキベースのメーカー その26 ESP
- まとめ
エレキベースのメーカー その1 Fender
フェンダーは1940年代にアメリカで設立されたメーカーで、エレキベースの基礎となるプレシジョンベースとジャズベースというモデルを開発したことで知られています。
プレシジョンベースもジャズベースも現在では多くのメーカーが作っていますが、オリジナルの魅力はやはり強く、プロアマ問わず、多くのミュージシャンがフェンダーのベースを愛用しています。
フェンダーの楽器には、生産国ごとにアメリカ製、メキシコ製、日本製がありますが、中でもメキシコ製がコスパが良いのでお勧めです。
エレキベースのメーカー その2 Fodera
フォデラは世界的な高級楽器ブランドで、多くのベーシストの憧れです。
力強いアクティブサウンドが特徴で、バランスがよく、高域のキラキラとした音色が心地いいです。
マーカスミラーやリチャードボナ、ヴィクターウッテンなど、多くのトップミュージシャンが愛用しています。
エレキベースのメーカー その3 Squier (by Fender)
スクワイヤーは、フェンダーの廉価版メーカーで、楽器はインドネシアなどで生産されています。
スタンダードなジャズベースやプレシジョンベースのほか、ミュージシャンのシグネイチャーモデルや、バリトンギターなど変わったモデルがあ流のも魅力です。
フェンダーに比べてだいぶ価格が安いですが、品質がよく、コストパフォーマンスが良いブランドです。
エレキベースのメーカー その4 ATELIER Z
アトリエZは日本のメーカーで、ジャズベースをベースにしたアクティブベース「M#」シリーズがよく知られています。
重みのあるアクティブサウンドが特徴で、ファンクやフュージョン、スラップに強いです。反応が早く、細かいフレーズもきれいに弾くことができます。
高い品質には定評があり、多くのミュージシャンが愛用しています。
エレキベースのメーカー その5 Bacchus
バッカスは日本の楽器メーカーです。
エントリーモデルからプロ使用まで、幅広く製造しています。
バッカスのベースは低価格帯のものでも仕上げが良く、弾きやすいので
初心者の方にもおすすめです。
サウンドはクリアで、どんなジャンルでも使えます。
予算を抑えて品質の良い楽器を探している方にはバッカスのベースがお勧めです。
エレキベースのメーカー その6 DINGWALL
カナダのハイエンドブランドです。
「ファン・フレットシステム」という斜めに貼られたフレットが特徴で、
これにより弦楽器特有の微小な音程のズレを解消しています。
いかにも弾きにくそうな見た目ですが、弾いてみると意外に違和感なく弾けます。反応が早く、キレのあるサウンドと音程の良さは演奏していて気持ちよいです。
音程をシビアに考えている方や、弾きやすい楽器を探している方にお勧めです。
エレキベースのメーカー その7 FUJIGEN
フジゲンはかつてフェンダージャパンの楽器を製造していたメーカーで、技術の高さと、品質の良さに定評があります。
細部まで丁寧に作られたフジゲンのベースはプレイヤビリティが高く、どのモデルもとても弾きやすいので、初心者の方にもお勧めです。
また、クリアでくせがないサウンドは、どんなジャンルの音楽にもマッチします。
エレキベースのメーカー その8 Gibson
ギブソンのエレキベースは、レスポールやSGなど、ギブソンの代表的なギターのモデルをそのままベースにしたものが多いです。
太くて甘いサウンドはギブソンのベースでしか出せない特有のもので、パンクやロックに良くマッチします。
使えるジャンルは限られますが、ギブソンのベースでしか味わうことができないサウンドはまさに唯一無二と言えます。
エレキベースのメーカー その9 Hofner
ヘフナーはドイツのメーカーで、ビートルズのポールマッカートニーが使っていたヴァイオリンベースで有名です。
ヴァイオリンベースはフェンダー系のベースより軽くて小さいので弾きやすく、アコースティックベースのような、サスティーンの短い弾むような
サウンドが特徴です。
ドイツ製と、廉価版の韓国製がありますが、サウンドや品質はどちらもそれほど変わらないです。こだわりがなければ韓国製のほうがリーズナブルなのでおすすめです。
エレキベースのメーカー その10 Ibanez
アイバニーズの楽器には愛好者が多く、世界中の多くのミュージシャンが愛用しています。
アイバニーズのベースは独自のデザインのものが多いですが、弾いてみるとボディのシェイプがいい感じで、軽くて弾きやすいです。
フラットでシャープなサウンドは、テクニカルなプレイがマッチする印象を受けます。
楽器の作りの良さと高級感のある見た目に対して値段は手頃で、コストパフォーマンスに優れているメーカーです。
エレキベースのメーカー その11 Xotic
Xotic(エキゾチック)はベースやギター、エフェクターなどを手掛けるアメリカの楽器メーカーです。
Xoticのベースには多機能かつ高性能な自社製のプリアンプが搭載されていて、ナチュラルなヴィンテージトーンから、ブースターの効いたアクティブサウンドまで、幅広いサウンドを作ることができます。
実際に弾いてみるとその音色の良さに驚きます。
操作性も良く、
ピックアップやピックガードの、
丸みを基調としたデザインが印象的です。
エレキベースのメーカー その12 LAKLAND
LAKLANDは1994年創業のアメリカのメーカーです。比較的若いメーカーですが、高い技術力と完成度の高いデザインで人気の高いブランドです。
代表的なモデルの44-94、55-94などは、フェンダーのスタイルを基にしながらも現代的なのデザインと電気回路を取り入れ、汎用性の高いサウンドと弾きやすさを実現しています。
また、44-60や44-64のようなヴィンテージスタイルのベースでも確かなクオリティを示し、技術力の高さを感じることができます。
現場での適応力が高く、ロック、ジャズ、フュージョンなど幅広いジャンルのミュージシャンが愛用しています。
東南アジアで作られているスカイライン、日本製ショアライン、USA製の3つのラインナップがあります。
日本製の楽器は、USA製と同じパーツで作られているのに価格はUSAより安く、お得感があります。
一方東南アジア製はさらに安いですが、パーツや材があまり良くないのであまりおすすめできません。
エレキベースのメーカー その13 MUSICMAN
ミュージックマンはアメリカのメーカーで、スティングレイというモデルが有名です。
ミュージックマン独自の高出力ピックアップによる、キレの良いパワフルなサウンドが特徴で、ファンク系など16ビートの音楽に良くマッチします。
また、スティングレイには廉価版のスターリングというモデルがありますが、スティングレイと比べてもサウンドや弾き心地に遜色なく、おすすめです。
エレキベースのメーカー その14 momose
momoseは日本のギターブランドです。
サウンドの傾向はヴィンテージトーンで、よく言えば上品でくせのない音で、どんなジャンルにも使えるサウンドです。
ただし、あっさりしすぎるサウンドでもあり、アンプやプリアンプで音作りをしないと抜けの悪い音になってしまいます。
また、momoseのベースは見た目も高級感があり、ヘッドの形やロゴが芸術的でかっこいいです。
エレキベースのメーカー その15 Moon
日本の楽器メーカーです。アクティブタイプのベースが有名で、フュージョン系の人がよく使っています。
ムーンの楽器は質の良いパーツを熟練のビルダーが国内で組み上げているため、品質が良いのが特徴です。
世界的に人気があるメーカーで、多くのミュージシャンが愛用しています。
エレキベースのメーカー その16 Rickenbacker
リッケンバッカーのベースはポールマッカートニーが使用したことで有名です。サウンドは抜けが良い硬質な音色で、演奏ジャンルが限られます。
フェンダーのジャズベースなどと違い、右手の親指を置く場所にも困る造りで、正直弾きにくいと感じます。
ビートルズファンなど、コレクターの方にはおすすめですが、ベーシスト(特に初心者の方)には正直あまりおすすめできないです。
エレキベースのメーカー その17 Sadowsky Guitars
サドウスキーはアメリカのメーカーで、マーカスミラーのベースをモデファイしたことでも有名です。
楽器のクオリティは最高で、仕上げが良く、とても弾きやすいです。
また、サウンドは芯があるブライトなトーンで、弾いていて心地よく、アクティブで弾いてもパッシブに切り替えてもどちらもとても良いサウンドです。
アジア製のメトロエクスプレスシリーズが品質も良く、値段が手頃でおすすめです。
エレキベースのメーカー その18 STEINBERGER
スタインバーガーは独創的な楽器メーカーです。
弦のペグをボディ側につけることでヘッドを無くし、さらにボディも小さくした、超コンパクトな楽器を作っています。
ただし、楽器はコンパクトでもサウンドは普通のベースと同じか、むしろパワフルなくらいです。
楽器としてのクオリティは高く、スティング他、プロミュージシャンも
数多く使用しています。
ちょっと変わったコンパクトなベースが欲しい方におすすめのメーカーです。
エレキベースのメーカー その20 Warwick
ワーウィックは、ドイツのベースブランドです。
ボディの形状が特徴的です。
造りががっしりしていて、仕上げも良く、丸いネックが弾きやすいです。
サウンドはクリアでパンチがあり、低音がしっかりした印象です。
廉価版のクオリティが高く、コスパが良いです。
エレキベースのメーカー その21 YAMAHA
ヤマハのベースはエントリーモデルからプロ用まで、幅広いラインナップがあります。
いろいろなモデルがありますが、どれも基本的にナチュラルなサウンドで、どんなジャンルでも使うことができます。
どのグレードの楽器も良いですが、エントリーモデルが安くて品質が良いのでおすすめです。
エレキベースのメーカー その22 Aria ProII
日本のメーカーで、品質の良い楽器をリーズナブルに提供しているメーカーです。ベースのラインナップはエントリーモデルから、高級機種まで幅広くあります。
サウンドはパワフルで抜けが良く、エッジの効いた音色でバンドの中でも埋もれません。安くて良い楽器を探している方におすすめのメーカーです。
エレキベースのメーカー その23 MAYONES
ポーランドの楽器メーカーです。
エッジの効いた上品なサウンドはどんなジャンルでも使えます。
バランスよく全音域が良く鳴り、弾いていて心地よい良いサウンドです。
日本にはあまり入って来ませんが、見かけたら試す価値のあるメーカーです。
エレキベースのメーカー その24 SPECTOR
スペクターはアメリカの楽器メーカーです。
ヨーロッパで製造しているEURO仕様のものと、本家のUSA製があります。
スペクターのベースは軽く弾いても低音が深くよく鳴り、アクティブだけど自然な音色で、エッジの効いたスピード感のあるサウンドが心地よいです。
エレキベースのメーカー その25 G&L
G&Lは、レオフェンダーが立ち上げたブランドです。
独自のコントロールとスイッチで、ジャズベース、プレシジョンベース、スティングレイのサウンドが再現できます。
しかも、オリジナルを凌駕する良いサウンドです。
いろいろなジャンルを演奏する方でも、G&Lのベースを使えば一本で賄えてしまいます。
エレキベースのメーカー その26 ESP
日本のメーカーで、ナビケーター、グラスルーツ、エドワーズ、LTDなどいくつかのブランドを価格帯ごとに展開しています。
それぞれのブランドごとにカラーが違いますが、どのブランドの楽器も造りが良いです。全体的に音はフラットで、クセがなく、汎用性が高いです。
まとめ
今回は、ベースを作っている各メーカーの特徴をまとめました。
こちらで紹介しているサウンドハウスや、アマゾンのレビューなども楽器選びの参考になるのでよかったら合わせて見てください。
以上、参考にしてもらえればうれしいです。
それでは、また。




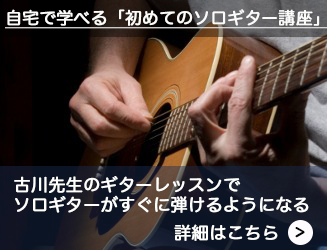






































































































































![ESP B155DX HNESP LTD B-155DX Honey Natural 5弦 エレキベース エレクトリックベース [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41GDsIBw3jL._SL500_.jpg)


コメント